
(写真:dutch/PIXTA)
2008〜09年の世界金融危機を受けて中国が用いた経済刺激策は国内総生産(GDP)比で12.5%に達する巨大なものだった。進歩派の経済学者たちは、これを全政府が見習うべき思い切ったケインズ主義の見事な手腕と考える傾向が強い。刺激策の結果生まれたコモディティーブームで潤った途上国だけでなく、世界銀行と国際通貨基金(IMF)も中国を褒めそやした。
ところが、より突っ込んだ経済研究が行われるようになると、もっと複雑な実態が判明し始めた。巨大な刺激策が短期的に有効だったことは否定できないが、同時にそれは中国の成長の質を歪め、多くの点で中国が現在直面している問題の原因となった。この発見をきっかけに、経済運営に政府が果たす役割を再考する動きが広まるようになっている。国家の指揮・統制が行き過ぎると、往々にして害が大きくなることが明らかになったからである。
この記事は有料会員限定です。
(残り 1168文字 です)
ログイン(会員の方はこちら)
有料会員登録
東洋経済オンライン有料会員にご登録いただくと、有料会員限定記事を含むすべての記事と、『週刊東洋経済』電子版をお読みいただけます。
- 有料会員限定記事を含むすべての記事が読める
- 『週刊東洋経済』電子版の最新号とバックナンバーが読み放題
- 有料会員限定メールマガジンをお届け
- 各種イベント・セミナーご優待
トピックボードAD
有料会員限定記事






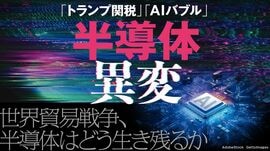








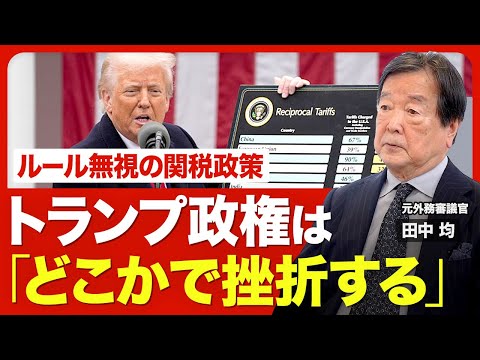





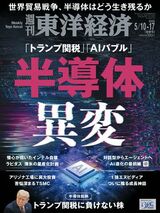










無料会員登録はこちら
ログインはこちら